障害者雇用ドットコム代表で東京情報大学の非常勤講師である松井優子氏の著書『障害者枠で働きたい人が知っておくべき就活の基本:障害者雇用アドバイザーが教える』をご紹介します。松井優子氏は特例子会社の立ち上げや200社以上の企業のコンサルティングや研修に携わり、企業視点の障害者雇用の進め方や業務の切り出し、職域開拓などを得意とします。この本は、障害者雇用を目指す人にとって非常に役立ちます。具体的な就職活動のノウハウを得ると同時に、障害者雇用の重要性や企業の視点も理解できる内容です。内容を簡潔にまとめましたので、最後まで読んでください!
第1章 就職活動をするにあたって知っておくべき基礎基本
障害者雇用と一般雇用の違い
障害者雇用は、障害を持つ人々が働くための特別な枠であり、一般雇用とは異なります。障害者雇用には、特別な配慮やサポートが求められる場合がありますが、最終的には企業のニーズや社会的責任としての側面が大きいです。
障害者雇用の状況
障害者雇用は年々進展しており、多くの企業が障害者を積極的に採用しています。ただし、全体の雇用状況としてはまだ課題も残り、企業によって取り組みが異なります。
日本における障害者雇用の経緯
日本では、障害者雇用の制度は法的な規制に基づき進展してきました。企業に一定割合の障害者を雇う義務が課せられているものの、その実施状況には差が見られます。
精神障害者の雇用が増えている理由
精神障害者の雇用が増えている背景には、社会的理解の進展や、企業の支援体制の改善が進んでいることが挙げられます。また、精神障害者が活躍できる仕事の選択肢が広がっていることも要因の一つです。
第2章 企業の障害者雇用の現場からみた現実
企業の担当者も障害者雇用に戸惑っている
企業の担当者も障害者雇用に関しては経験が少なく、戸惑っていることが多いです。障害者に対する理解が足りない場合もあり、企業全体としての対応力に差が出ることもあります。
「障害者雇用をしている会社は障害者に理解がある」は間違い
障害者雇用をしている企業でも、実際には障害者に対する理解や配慮が十分でない場合があります。雇用していること自体が理解のある態度とは限らないため、企業ごとの実態を見極める必要があります。
なぜ、障害者枠で雇用されているのに理解がないのか
障害者枠で採用されている場合でも、企業の担当者や同僚が障害について十分に理解していないことがあります。理解不足のまま雇用されることが、職場でのコミュニケーションや作業環境に問題を引き起こすことがあるためです。
「障害者だから配慮してほしい」では、真意は伝わらない
自分の障害に対する配慮を求める際には、ただ「配慮してほしい」と伝えるだけではなく、具体的に何をどのように配慮してほしいかを明確に伝えることが重要です。自分のニーズを理解してもらうためには、具体的な説明や提案が必要です。
第3章 知っておきたい合理的配慮
企業に求められている合理的配慮とは
合理的配慮とは、障害者が能力を最大限発揮できるようにするための調整です。企業には、業務の内容や職場環境の調整など、合理的な配慮を行う義務があります。
合理的配慮を受けるために必要なこと
合理的配慮を受けるためには、自分の障害についての正しい理解と、自分が必要としている配慮内容を具体的に伝えることが大切です。また、企業との信頼関係を築き、双方で協力して問題解決に取り組む姿勢が求められます。
障害に対する理解はコミュニケーションから始まる
障害者と企業の間で理解を深めるためには、コミュニケーションが非常に重要です。自分の障害に関してオープンに話し、必要な配慮について理解してもらうことが、円滑な就業に繋がります。
第4章 安定的な就労を続けるために
企業は支援機関とのつながりを重視している
企業は障害者雇用に関して支援機関と連携を強化しています。支援機関は、企業が適切な配慮を行うためのアドバイスや、問題が起きたときの相談窓口として重要な役割を果たします。
あなたに合う職場を見つける
自分に合った職場環境を見つけることが、安定した就労に繋がります。企業が求める能力と自分の特性をうまくマッチさせることが、長期的な成功の鍵です。
会社の評価を受けとめる
企業からの評価は、就業の成否に直結します。自己改善のために、フィードバックを受け入れ、必要なスキルや態度を身につけることが重要です。
まとめ
このように、障害者枠で働くための実践的なアドバイスや心構えが、この本には詰まっています。自分のニーズを理解し、企業とのコミュニケーションをしっかりと取りながら、安定的な就労を目指すための手助けとなる内容が豊富です。障がいのある方の手助けとなりますので、是非読んでみてください!
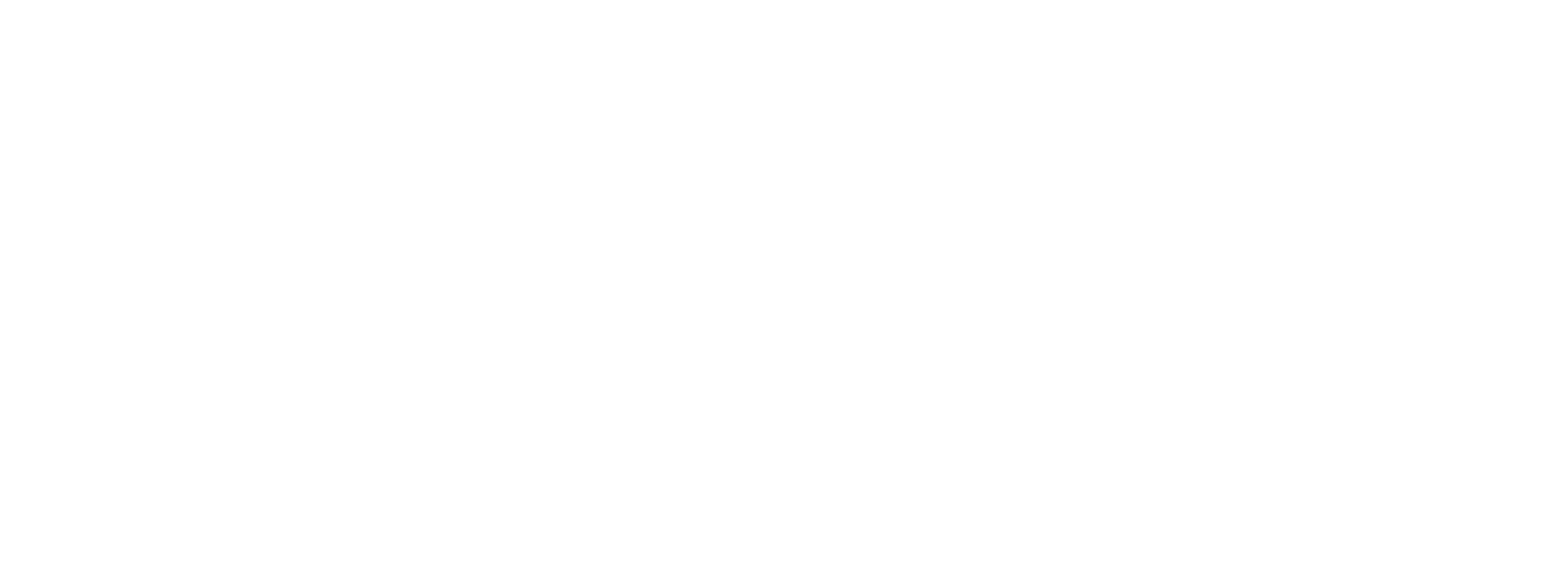
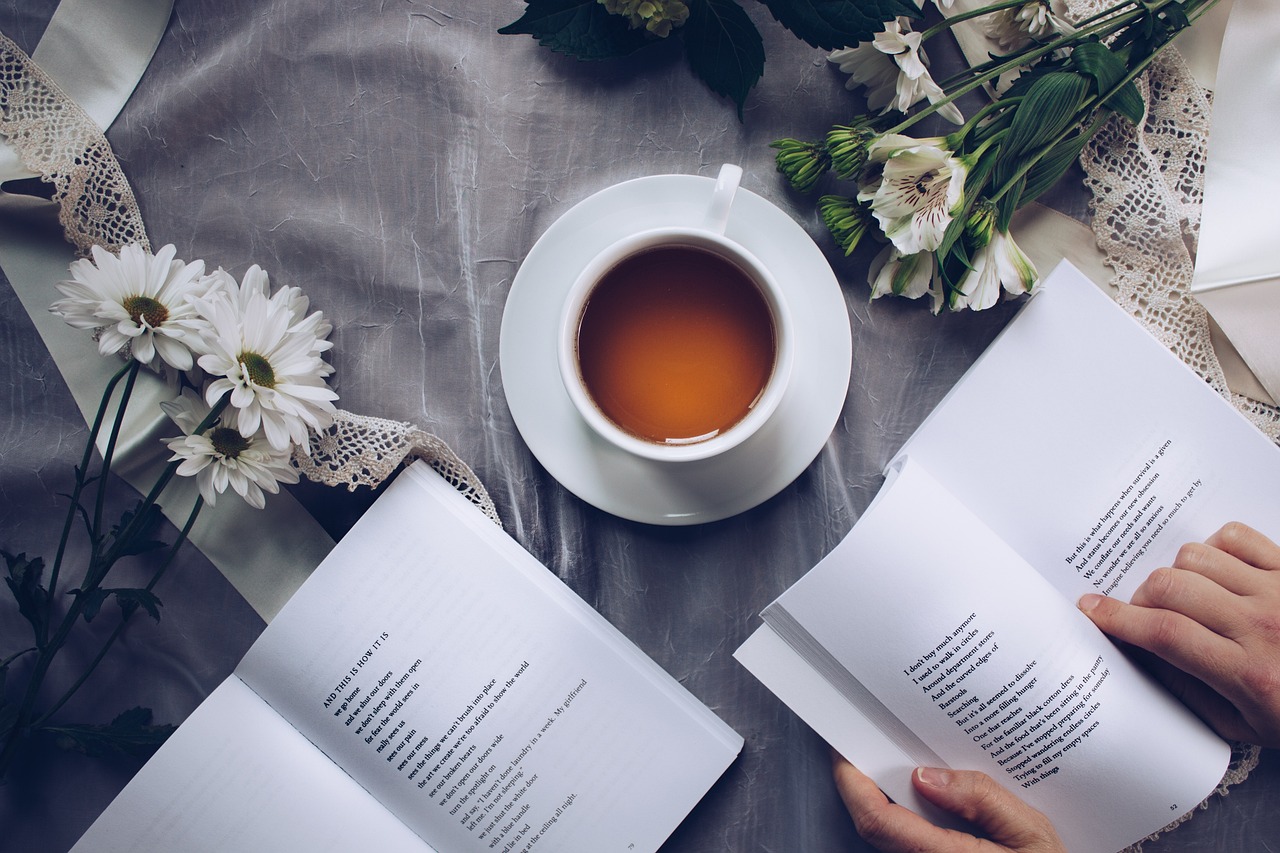


コメント